設問1
第1 甲がYにブドウを取ってくるよう言った行為1に窃盗未遂罪(235条・243条)の間接正犯は成立しない。
1 間接正犯性が認められるかは、被利用者に規範的障害があったかや利用者が被利用者を一方的に支配利用していたかを総合考慮する。
Yは6歳で万引きが悪とわかってるだろうし、実際にちゅうちょしたから規範的障害がなかったとは言えない。しかし、6歳のYにとって35歳の母親甲の存在は大きく、甲がYに強い口調で言ったら怖くなって甲の指示に従うことに決めたことから、甲がYを一方的に支配利用する関係にあったと言える。
よって、間接正犯性が認められ、Yの店内に入ってブドウを探し回る行為2は行為1の延長と見ることができる。
2 未遂犯の趣旨は、法益侵害の現実的危険から法益を保護する点にある。そこで、法益侵害の現実的危険性が生じたら実行の着手(43条本文参照)があったといえると解する。
Yは約10分間掛けてC内を探したが、果物コーナーの場所がわからず、そのまま何も取らずに店を出た。さっき行ったばかりの場所とはいえ、Cは大型のスーパーであり、Yは6歳と未熟であり、実際に果物コーナーまで行けなかったのであるから、行為2だけでは窃盗罪の保護法益たるブドウの占有権侵害の現実的危険が生じたとは言えない。
よって、窃盗罪の実行の着手はないので、同未遂罪は成立しない。
3 よって、その間接正犯も成立しない。
第2 甲がXにCのステーキを取ってくるように言った行為3に牛肉5パックに関する窃盗罪の共同正犯が成立する(60条)。
1 XはYより7歳も年上だから規範的障害があるといえる。
13歳にとって35歳の母親は6歳の子ほど大きな存在ではないし、Yのように怖くなったわけではなく、渋々応じたに過ぎない。また、XはCでどうせなら多い方がいいだろうと考えて甲が言った2パックではなく5パック取り、甲に言われなかった写真集も取って、現場で臨機応変に動いている。よって、Yと違って、甲がXを一方的に支配利用する関係にはない。
よって、甲に窃盗罪の間接正犯は成立しない。
2 甲からXに上記のように積極的に働きかけており、「3000円くらいのやつを2パックとってきて。」と具体的に指示をし、警備員の休憩時間という重要な情報も提供し重要な役割を果たしている。さらに、牛肉を受け取り食べているから、積極的に犯行に加担する動機があったことが伺われる。よって、自己の窃盗罪として積極・主体的に犯行行う「正犯」意思が認めれる。甲がXに説得をして、Xは「分かった」と言い意思連絡があるから、「共同~実行」の意思も認めれれる(併せて共謀)。
3 牛肉5パックも本件写真集もBという「他人」(235条)がCで占有する「財物」である。Xはこれらを精算することなく店外に持ち出したからBの意思に反する占有移転があったといえ、「窃取した」と言える。行為態様から牛肉5パックと写真集に関する同罪の故意(38条1項本文)も認められる。
4 Xの上記Cでの行為4は上記共謀に基づくか。
牛肉5パックは、甲が言った牛肉2パックと数が変わるに過ぎない。また、2パックより多く取ることを禁止していないし、冷凍する方法もあるし多い分には甲は困らないだろう(実際に全て食べている)。そうすると、牛肉5パックに関する行為4は上記共謀に基づくから「共同~実行」の事実が認められる。
同写真集は、Bの占有する財物であり、牛肉5パックを取った行為も同写真集を取ったのもC内であり時間的場所的に接着している。しかし、牛肉は食品である一方で、同写真集は食品ではないため、異質である。甲は当初「今晩ステーキが食べたいね」と言って牛肉を取るように言い、さらに同写真集はXの好きなアイドルのものだから同写真集を取ることは想定していないと考えられる。また、Xは同写真集をにわかに欲しくなったものだから、新たな犯意に基づいて取ったものである。そうすると、同写真集に関する行為4は上記共謀に基づくといえず、「共同~実行」の事実も認められない。
5 故意責任の本質は規範に直面したのにあえて行為をしたことに対する非難にある。そして規範は構成要件として与えられているから構成要件の範囲内で主観と客観が符合すれば故意が認められると解する。
甲の主観たる牛肉2パックと客観たる5パックは、「財物」という構成要件の範囲内で符合している。
よって、牛肉5パックに関する同罪の故意が認められる。
6 Xは13歳で「14歳に満たない者」で責任能力がないが、「違法は連帯に、責任は個別に」から甲のXとの間で共同正犯は認められる。
設問2
第1 事後強盗が既遂かどうかは窃盗が既遂かどうかで判断すると解する。「強盗として論ずる」(238条)以上、財物奪取を基準とすべきだからである。
本件テレビ1箱を甲は自己のトートバッグに入れて、出入り口方向へ歩き出そうとした。しかし、まだバッグに入れて歩き出そうとしたに過ぎない。また、同箱は、50センチメートル×40センチメートル×15センチメートルという相当程度の大きさであり、同バッグから10㎝ほどはみ出した状態になっていた。そうすると、占有者Dの意思に反する占有移転があったとは言えないから、「窃取した」と言えず窃盗罪の既遂になっていない。よって、仮に事後強盗罪が成立するとしても未遂である。
第2 窃盗未遂でも財物を取り返されることを防ぐなどの目的のために暴行・脅迫を加えることが予想される。よって、「窃盗」(238条)と言うためには、実行の着手で足りる。上記のように同箱を同バッグに入れていることから、本件テレビの占有権侵害の現実的危険があると言え、甲は窃盗罪の実行に着手した「窃盗」と言える。
窃盗の機会の暴行・脅迫だからこそ、暴行・脅迫による財物奪取と評価できる。そこで、暴行・脅迫は窃盗の機会に行われたことを要する。
甲の上記「窃盗」の18分後に隣接する駐車場で行われた甲がFを押す行為は、少なくとも「窃盗」と場所的に接着している。しかし、元々甲は「窃盗」の場から走って逃げだし、Eを出てから約3分後、Eから約400メートル離れた公園にたどり着き、同所でEから追ってくる人がいないかうかがっていた。甲は、約10分間、上記公園にとどまっていたが、誰も追ってこなかった。よって、この時点で安全圏に入ったと言える。よって、窃盗の機会性が失われたから、甲がFを押した行為が「暴行」だとしても、それは窃盗の機会に行われたものではないため、事後強盗罪は成立しない。
第3 「暴行」とは、社会通念上相手方の反抗を抑圧するに足る程度をいう。
甲は武器を使わずに両手でFの胸部を1回押したに過ぎない。結果的にFは体勢を崩して尻もちを付く程度に過ぎなかった。甲とFは同じ35歳女性であり体力等は拮抗していると思われる。よって、上記押した行為は社会通念上相手方の反抗を抑圧するに足る程度と言えないから、「暴行」に当たらず、事後強盗罪は成立しない。
以上
【感想等】
犯罪が少なく、答案構成がかなり早く終わる問題でした。
ただ、設問2は予備試験では初めての問題形式でそこは面食らうでしょうね。
でも難しい学説は不要で、事後強盗罪の構成要件を1つずつ検討して、要件を満たさないところをピックアップしていけば自ずと答えが書けます。
※この記事を読んだ人は下記記事も読んでいます。

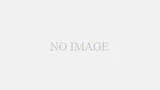
コメント