1 本件立法は報道関係者の取材の自由(以下「自由1」)を制約するが、違憲ではないか。
2 事実の報道と思想・意見の伝達との区別は困難だから、報道の自由は思想・意見”等の情報”を外部に伝達する「一切の表現の自由」(21条1項)として保障される。取材は報道の手段だから、自由1も同条項で保障される。
3 としても「公共の福祉」に基づく最小限の制約に服す(13条後段)。ここで最小限の制約かどうかの審査基準が明らかでない。
(1)表現の自由は一旦侵害されると民主政の過程で是正困難な精神的自由権である。
報道の自由は国民の知る権利に資する重要なものである。しかし、自由1は、報道の自由の手段に過ぎないため、重要とは言えない。
(2)本件立法は、自宅・勤務先等への訪問、電話、ファックス、メール、手紙、外出時の接近等というあらゆる手段での取材等を禁止しており、この点で規制態様は強い。
しかし、犯罪被害者等の同意があれば取材は禁止されないから一律的な制約ではない。また、捜査機関は、捜査に当たる場合には、犯罪被害者等が取材等に同意するか否かについて確認し、報道関係者から問合せがあった場合には回答するものとするほか、犯罪被害者等が希望する場合には、その一部又は全員が取材等に同意しないことを記者会見等で公表することもできる。よって、報道関係者に不意打ち的な制約にならない。これらの点で規制態様は弱い。
(3)そこで、中間的な基準、具体的には重要目的と実質的関連性ある充分合理的な手段による制約なら最小限と解する。
4(1) 報道機関による取材活動については、一般にその公共性が認められているものの、取材対象者の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ、とりわけ、特定の事件・事象に際し取材活動が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて、何らかの対策がとられる必要があると指摘されてきた。中でも、取材活動の対象が、犯罪被害者及びその家族等となる場合、それらの者については、何の落ち度もなく、悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから、報道機関に対して批判が向けられてきた。そうすると、犯罪被害者及びその家族等の生活の平穏は人格的生存に不可欠なプライバシー権と言える(13条後段)。その保護という本件立法の目的は自由1制約に値するほど重要である。
(2)本件立法は上記のように取材を禁止するものだが、まずは「被害者等のプライバシーに配慮して取材をする」などの誓約を届け出た者に取材を許可するような方法にして、問題があれば行政指導をして、それでも問題があれば中止命令を発令することも考えられる。しかし、心の傷を負うと回復困難であるし、上記批判があることから、禁止にする必要性が大きく、禁止にしないと上記目的を達成できない。
また、本件立法は罰則があるため、過剰とも思える。しかし、直ちに処罰されるわけではなく、処罰されるのは取材等中止命令が発出されているにもかかわらず、取材等を行った場合のみであるから段階的なものに過ぎない。そして上記目的達成のために実効性確保の観点から罰則もやむを得ない。さらに、中止命令は、行政手続法等の定めるところに従い憲法上適正な手続(31条参照)を履践した上で発せられるから自由1が不当に制約されるわけでもない。
犯罪被害者等は、取材等中止命令の解除を申し出ることができ、その場合、当該命令は速やかに解除されるから不可逆的に取材が制約されるものでもない。
そうすると、本件立法は、上記大きな必要性と比べると相当といえ、上記目的と実質的関連性ある充分合理的な手段と言える。
5 よって、本件立法は、最小限の制約だから合憲である。
以上
【感想等】
本問は予備試験憲法の中でも易しめです。しかし、それゆえか、本番いろいろ書いてしまってF評価でしたね。。
今回の答案を見てわかると思いますが、審査基準定立前はかなりシンプルです。
抽象論であり、特に生の自由に関して事案に即して検討できていません。
しかし、これでいいんです。
どういうことかというと、この審査基準定立段階で事案に即して具体的に書こうとすると、時間が足りなくなるからです。
それと、シンプルに難易度が高い(そこで頭をひねっても思いつかない)。
ぼくは受験生時代にこの審査基準定立段階で何度も事案に即して書けるよう頑張りました。
しかし、鍛錬に鍛錬を重ねても無理でした。
ぼくの事務処理能力・頭では限界があったんです。
そこで、審査基準定立前はシンプルにして、当てはめで勝負できるように腹を決めました。
まあ実際に抽象論オブ抽象論で書いた令和元年はA評価が来てますからね。
変に敵を強大に考えすぎないのが良いです。
あと、審査基準定立前にガチャガチャ書くと論理矛盾が怖い。ここは抽象論レベルだからね。
一方で当てはめは具体レベルなので、自由度が高いです。
ちなみに、審査基準を「厳格」や「緩やか」にするとそれで答案の方向性が決まって、何というか張り合いのない答案になるのかなと(「そりゃあ結論は合憲(違憲)だよね。」みたいな)。
それに、「不可欠目的」って難しくないですか?
そこで、中間の基準に敢えてして、違憲・合憲のどちらにも持って行けるようにするのがオススメです。
つまり、中間の基準にすることで、「審査基準定立段階で書けることでも敢えて書かない」というスンポーですね。
基準定立段階で使えなかった事情も当てはめで使えるので、問題なしです。
※この記事を読んだ人は下記記事も読んでいます。

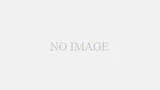
コメント