第1 Aが甲に覚せい剤を申し込んだ行為1は、おとり「捜査」(189条2項)の一環だが、「強制の処分」(197条1項但書)にあたるか。
1(1) 「強制の処分」とは、(a)その文言と(b)物理的実力によらない捜査からも個人の人権を保障する一方で、軽微な権利利益の制約では法定手続きの拘束なく真実発見を図るべき(1条)だから、(a)相手方の合理的意思に反し、(b)その重要な権利利益の制約を伴う処分と解する。
(2) (a)甲の検挙を意図してされた行為1は甲の合理的意思に反する。(b)しかし、甲に覚せい剤販売を強いたわけではないため、自己決定権(憲法13条後段)等の重要な権利利益の制約を伴う処分とは言えない。
(3) よって、「強制の処分」にあたらない。
2(1) としても、正当な「捜査~目的を達するため」の「必要」性と見合う権利利益の制約でないと、相当と認められない(197条1項本文:比例原則)。
(2) 行為1は覚せい剤犯罪の証拠の収集・保全という正当な「捜査~目的を達するため」にされた。
本件のような薬物犯罪は密行性が高く、実際にAの甲から覚せい剤購入を持ち掛けられたことがある旨の供述及び通常の捜査方法のみでは甲の検挙が困難だった。また、甲は暴力団員であることから薬物犯罪に加担する傾向が強く、上記情報と相まって嫌疑が強い。よって、同目的を達するための必要性が大きい。
甲はグラム数や値段、時間帯を具体的に明示して自発的に答えていた。そうすると、機会があれば覚せい剤販売を行うつもりだっただろうからその機会を提供したに過ぎない行為1は上記甲の重要でない権利利益制約と見合う相当なものである。
3 よって、行為1は適法である。
第2 1 Aが甲の姿及び発言内容をひそかにビデオカメラに録音録画した行為2もおとり捜査の一環だが、「強制の処分」に当たるか。
(1) (a)第1の1(2)と同じく行為2も甲の合理的意思に反する。(b)しかし、甲は喫茶店という誰でも立ち入りできて見られる場所におり、そこでの会話内容も周囲が認識しうる。また、会話内容の秘密性は相手に委ねられている。そうすると、行為2は甲のプライバシー権(憲法13条後段)等の重要な権利利益の制約を伴う処分とは言えない。
(2) よって、行為2は「強制の処分」にあたらない。
2 第1の2(2)と同じく行為2は「捜査~目的を達するため」に行われた。
第1の2(2)の事情だけではなく、甲が覚せい剤と絡んでいることを証拠として残すために甲との会話を録音する必要性があった。また、薬物犯罪は秘密裏に会話なしで行われることも想定されるため、その姿を撮る必要もあった。以上から、同目的を達するための必要性が大きい。
Aと甲の会話内容から録音録画は長時間されたものと認められない。録音録画したものが目的外に使われる恐れがある事情もない。
よって、行為2は上記甲の重要でない権利利益制約と見合う相当なものである。
3 よって、行為2は適法である。
以上
【感想等】
本問は易しめの問題です。
予備刑訴はH23がやや特殊なので、このH24をまずしっかり処理手順に沿って書けるようにしておきましょう。
そのうえで、いろいろな参考答案や再現答案から、比例原則の当てはめの書き方を学んでください。そこで差がつきます。
※この記事を読んだ人は下記記事も読んでいます。

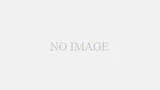
コメント