設問1
第1 「行政指導に携わる者は」、「申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を」真摯かつ明確に「表明したにもかかわらず当該行政指導~継続~等により当該申請者の権利の行使を妨げるような」場合、「当該申請者」が受ける不利益と「当該~指導」の目的とする公益上の必要性とを比較衡量し、「当該~指導」への「当該申請者」の不協力が社会通念上正義の観念に反する特段の事情のない限り、「当該~指導~継続~等」をするのは違法と解する(行手法33条)。
第2 AはBの紛争を円満に解決するように求める行政指導を受けて、住民に説明会を開催し、本件調査書に基づき本件処分場の安全性を説明するとともに、住民に対し、本件提案もした。それでも円満な解決に至らなかったため、「申請者」Aは「行政指導に携わる者」Bに対して上記行政指導にはこれ以上応じられないので直ちに本件申請に対して許可をするように求める旨の内容証明郵便を送付したから、これで同行政指導に「従う意思がない旨を」真摯かつ明確に「表明した」といえる。にもかかわらず許可を留保するのは、「当該行政指導~継続~等により当該申請者の権利の行使を妨げるような」場合といえる。
なお、たしかに本件内容証明郵便送付後もAは行政指導に従って月1回程度の説明会を開催して再度本件提案をするなどして住民の説得を試みてはいた。しかし、これは建築資材上昇による損失を回避するためにやむを得ず行ったものである。
第3 しかし、上記説明会でAが(ア)住民のように装ったA社従業員を説明会に参加させ、本件処分場の安全性に問題がないとする方向の質問をさせたり意見を述べさせたりし、(イ)あえて手狭な説明会場を準備し、賛成派住民を早めに会場に到着させて、反対派住民が十分に参加できないような形で説明会を運営した、という行為に及んでいたから本件行政指導へのAの不協力が社会通念上の正義の観念に反する特段の事情があるのではないか。
たしかに(ア)住民のように従業員をよそわせるのは欺く行為ともいえるが、A側の主張をスムーズに伝える手段に過ぎない。(イ)反対派住民が十分参加できないような形で説明会を開催した点もフェアではないとも思えるが、まったく参加できないようにしたわけでもない。
そして本件申請が法第15条の2第1項所定の要件を全て満たしていると判断されている以上は、本件行政指導の目的は紛争の円満な解決すぎないため、その公益上の必要性は大きくない。一方で本件留保が続くと、建築資材価格が上昇しAの経営(憲法22条1項参照)という重要な利益を圧迫するおそれが生じていた。これらを比較衡量すると、上記特段の事情があるとは言えない。
第4 よって、本件内容証明郵便到達時点で本件申請に対する許可の留保は違法である。
設問2
第1 本件許可「処分~の相手方以外の者」(行訴法9条2項)であるC1及びC2は「処分~の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」(同1項)として原告適格が認められるか。
第2 「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利・法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのあるものと解する。そして当該処分を定めた行政法規が不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここに言う法律上保護された利益にあたると解すべきである(9条2項参照)。
第3 本件許可の根拠規定たる法15条の2第1項の趣旨・目的は、「生活環境の保全」(同2号)と解される。これは法1条(目的)にも「生活環境の保全」と書かれていることからうかがわれる。
第4 1 本件許可が違法にされたら、有害物質の地下水への浸透や飛散により「生活環境」が害され、健康が害されることが考えられる。「生活環境」が反復・継続的に害されると、被害は重大なものになり、健康は一度失われると回復困難なものである。
2 とすると、法15条の2第1項は、有害物質の地下水への浸透や飛散による著しい被害が直接的に及ぶことが想定される「生活」や健康を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解すべきである。
3(1) たしかにC1の居住地は、本件調査書において、対象地域に含まれていない。また、仮に本件処分場の有害物質が風等の影響で飛散した場合、それがC1の居住地に到達するおそれの有無については明らかでない(②)。しかし、仮に本件処分場の有害物質が地下水に浸透した場合、それが下流側のC1の居住地に到達するおそれは認められる(①)。C1は地下水を飲用していないものの、居住地内の果樹園で地下水を利用して新種の高級ぶどうを栽培している。そうすると、C1は、有害物質の地下水への浸透により、高級ぶどうが汚染されて果樹園の経営が立ち行かなくなり、生活に著しい被害が直接的に及ぶことが想定される。よって、C1は、本件許可により法律上保護された上記「生活」を必然的に侵害されるおそれのある「法律上の利益を有する者」として原告適格が認められる。
(2) たしかに有害物質が地下水に浸透した場合、それが上流側のC2の居住地に到達するおそれはない(①)し、飛散した場合にそれがC2の居住地に到達するおそれの有無については明らかでない(②)。しかし、C2は、本件予定地から上流側に約500メートル離れた場所に居住しており、本件処分場から約2キロ離れているC1より近くに住んでいる。また、C2の居住地は本件調査書において、生活環境に影響を及ぼすおそれがある対象地域に含まれている。そうすると、C2は有害物質の飛散により、その健康に著しい被害が直接的に及ぶことが想定される。よって、C2は、本件許可により法律上保護された上記健康を必然的に侵害されるおそれのある「法律上の利益を有する者」として原告適格が認められる。
以上
【感想等】
論じることが満載の原告適格などでは、「論じたいこと」の中から、欲張らずに削ぎ落して一定の答案を完成させる必要があります。
典型的な答案の型を学びつつ、上記の練習をしておきましょう。
※この記事を読んだ人は下記記事も読んでいます。

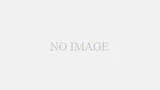
コメント