設問1
(1)ア
第1 BはAに対する甲債権不存在確認請求とCに対する乙債権支払い請求をすることが考えられる。
第2 共同訴訟参加(52条)としてできないか。
1 そもそもAに訴訟1の当事者適格が認められるのは、甲の「債権者」Aが「自己の債権を保全するため必要がある」として「債務者」Bに「属する権利」たるその訴訟物の乙債権の管理処分権がAに帰属し、法定訴訟担当が認められるからである(民法423条1項本文参照)。
しかし、「債権者」Aが「被代位権利を行使した場合であっても、債務者」Bは「自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」から、Bにも管理処分権が帰属して当事者適格が認められる。
2 52条1項の趣旨は裁判矛盾防止にあるから「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合」とは、両者間に判決効が及ぶ場合と解する。
訴訟1の判決効は、「当事者」A(115条1項1号)だけではなく、上記のように「当事者」Aが「他人のために原告~となった場合のその他人」B(同2号)にも及ぶから、AB間に判決効が及ぶといえ、「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合」と言える。
3 よって、Bは共同訴訟参加は認められる。
もっとも、その必要的共同訴訟となる訴訟1において「甲債権不存在」の主張はAに不利益だから「全員の利益」とは言えないため、効力が生じない(40条1項)。そのため、共同訴訟参加をしてもBは満足を得にくい。
第3 独立当事者参加できないか(47条1項後段)。
1 同規定の趣旨は、3人以上のものが対立する状況で紛争の一挙統一的解決を図る点にある。そこで、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」とは、係属する請求と「自己」の請求が論理的に両立しない者と解する。この場合に紛争の一挙統一的解決が必要だからである。
2 訴訟1の「訴訟の目的」は乙債権であり、Aの請求とBのCに対する請求は同時に認められ得る。また、上記のようにAもBも当事者適格を有する。
よって、Bは係属するAの請求と「自己」の請求が論理的に両立しない者と言えず、独立当事者参加が認められないとも思える。
3 しかし、独立当事者参加は準独立当事者参加が認められていることから、本訴原告の請求認容で不利益を受ける第三者に、本訴牽制のための訴訟追行の地位・機会を与える機能もある。そこで、そのような第三者は47条1項後段を類推適用できると解する。
BはAの請求が認められると自己に支払いを受けられず不利益を受ける(民法423条の3参照)から、47条1項後段を類推適用できる。
4 よって、独立当事者参加は認められる。
第4 共同訴訟参加はできるが、上記から独立当事者参加を事実上することになる。
(1)イ
第1 Aが提起した訴訟1
Aの当事者適格の基礎たる甲債権を欠くことになるので、訴え却下判決をすべきである。
第2 Aに対する甲債権不存在確認請求
訴訟物たる甲債権が存在しないことから、請求認容判決をすべきである。
第3 Cに対する乙債権支払い請求
訴訟物たる乙債権が存在するため、請求認容判決をすべきである。
(2)甲債権が存在していたと判断したとき
訴訟1の確定判決の「既判力」は、「主文に包含するもの」、つまり基準時における訴訟物たる乙債権が存在しないとの判断に既判力が生じる。後訴裁判所たる訴訟2の裁判所は、この既判力で確定された事項と反する判断ができない(積極的作用)。これは紛争蒸し返しを防ぐため(a)で、前訴での当事者への手続き保障により正当化される(b)。
この既判力は「当事者」(115条1項1号:相対効)ACにのみ及ぶのが原則である。対立当事者にのみ既判力を及ぼせば紛争解決には十分だし(a)、手続き保障を欠く第三者に既判力を及ぼすと、その裁判を受ける権利(憲法32条)が害されるからである(b)。
しかし、上記第2の2にあるように「他人」B(同2号)にも既判力が及ぶ。CがBから乙債権について紛争を蒸し返されるの防ぐ必要がある(a)し、BはAに代替的に手続き保障があったといえるからである(b)。
よって、乙債権の支払いを求める訴訟2に関して、請求棄却判決をすべきである。
(2)甲債権が存在していなかったと判断したとき
上記(1)と同様にBに既判力が及ぶとも思える。しかし、甲債権が存在しない以上は、Aは当事者適格の基礎を欠くため、BはAにより代替的に手続き保障されていたとは言えない。よって、Bに既判力は及ばない。
よって、審理の結果、乙債権が認められるか否かで請求認容・棄却判決をすべきである。
設問2
第1 1500万円の売掛金債権の支払いをCに求める請求を立てて共同訴訟参加できないか。
設問1第2の1からBが当事者適格を失わない以上、「債権者」Dも当事者適格が認められる(民法423条1項参照)。
「他人」B(115条1項2号)を介して「当事者」のA・Dに判決効が及ぶ(同1号)から、「訴訟の目的」たる乙債権が「当事者の一方」たるA及び「第三者」Dについて「合一にのみ確定すべき場合」といえる。
よって、共同訴訟参加は認められる。
第2 第1と同じ請求を立てて、準独立当事者参加できないか(47条1項後段)。
DはBの請求が認められると自己に支払いを受けられず不利益を受ける(民法423条の3参照)から、47条1項後段を類推適用できる。
よって、準独立当事者参加は認められる。
以上
【感想等】
予備民訴の中では、チャレンジしやすい問題です。
ただ、それでも最初は難しいです。
民訴は多くの受験生が苦手意識を持つ科目なので、再現答案から相場を把握するようにしましょう。
なお、本問は民法(債権法)改正の影響を受けるので、当時の再現を読む際は注意が必要です。
※この記事を読んだ人は下記記事も読んでいます。

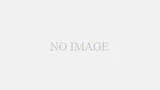
コメント