設問1
第1 1 本問借入れは5億円と多額で、急きょ10億円の資金が必要となったX社からしても大きな金額である。よって、「多額の借財」(会社法362条4項2号)にあたるから、取締役会決議を要する。
2(1)「特別の利害関係」(会社法369条2項)とは、決議の結果につき会社の利益と矛盾・衝突するような個人的利害関係と解する。
(2) Bは本問借入れのX社の相手方たるY社の創業者・取締役で、Y社で影響力ある人物であり、その発行済み株式の総数の90%という大半を有している。また、Y社のX社に対する貸付金の原資はBが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円であり,Bは,この5億円をそのままY社に貸し付けていた。そうすると、同借入れにおいてBはY社と実質的に同視できる。また、Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされているから、本問借入れは、その上乗せの分の90%(BのY社持分)がBに利益となりX社に不利益となる。よって、同借入れに関する決議の結果につき、BはX社の利益と矛盾・衝突するような個人的利害関係があるといえるから、「特別の利害関係」があるといえる。よって、同条項違反がある。
3(1)同条項の趣旨は、取締役の忠実義務(355条)違反を防ぎ、決議の公正を確保する点にある。とすると、同条項違反は重大な瑕疵と言えるから、決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情がない限り、一般原則により無効と解すべきである。
(2)Bは「議決に加わることはできない」だけで、審議には参加できる(同条項反対解釈)から元々決議に影響を及ぼし得る。すると、どのみちBを除いた出席取締役4名中3名が賛成し可決した(369条1項)といえる。よって、決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるから、無効ではない。
4 よって、この点で本問主張は、否である。
第2 1(1) 間接取引(356条1項3号)との区別から形式的に、「自己又は第三者のために」とは、自己又は第三者名義で、と解す。
(2) 本問借入れは、上記第1の1(2)のようにY社とBを同視できる事情があるものの、X社とY社の名義で行われている。また、Bは創業者ではあるものの、代表権のない取締役に過ぎないため、Y社のために取引したとも言えない。よって、「取締役」Bが「自己又は第三者」Y社名義でX社と取引をしたとはいえない。
2 上記第1の1(2)から、本問借入れは、「株式会社」X社が「取締役以外の者」たるY社との間においてX社と「取締役」Bとの利益が相反する取引といえる(同条項3号)。そうすると、Bは、取締役会設置会社X社(2条7号)の取締役会で上記利益相反に関する重要時な事実を開示し、その承認を受けなければならない(同条項柱書、365条1項)。しかし、Bは,同事実をX社の取締役会において説明していなかったから、同条項違反がある。
3(1) 会社利益保護のため、同条項違反は、利益相反した取締役との関係では無効である。しかし、取引安全のため、第三者との関係では、第三者が開示や承認の手続きを経ていないことに悪意・重過失であることを主張・立証しなければ、有効と解する。
(2) Y社は上記のようにBと実質的に同視できるから、上記手続きを経ていないことに悪意と言える。よって、これを主張・立証することで、本問借入れは無効と言える。
4 よって、この点で本問主張は妥当である。
設問2
1 既発行新株の取引安全から、重大な「法令又は定款に違反する場合」(210条1項1号参照)のみ募集株式発行の無効原因になると解する(828条1項2号)。
2(1) 「特に有利な金額」(199条3項)とは、「公正な価格」(212条1項1号参照)に比し特に低い金額と解する。そして資金調達の必要性と既存株主の利益保護の調和から、「公正な価格」とは前者が達せられる限度で、既存株主に最も有利な価格と解する。
(2) X社の募集事項の決定時及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は,1万円を下ることはなかった。そうすると、1株当たりの払込金額を5000円という半額で発行された本件募集株式は、資金調達目的が達せられる限度で、既存株主に最も有利な価格(「公正な価格」)に比し、特に低い金額と言える。よって、「特に有利な金額」にあたる。
3 そうすると、X社が公開会社(2条5号)とはいえ、募集株式の「払込金額」は株主総会で理由を説明し、特別決議で決めなければならない(201条1項、199条1項2号・2項、309条2項5号)。しかし、それらの手続きを経なかった。
4 しかし、株主総会の欠缺は、内部的意思決定に過ぎないため、取引安全から、重大な法令違反とは言えないと解する。
5 よって、本問主張は否である。
以上
【感想等】
本問は予備試験商法で最もオーソドックスな問題です。
なので、まず起案するのは本問がオススメです。
ちなみに、「特に有利な金額」に当たることは明らかなので、本問で解釈論を展開する必要性は乏しいですね(一応書きましたが)。
※この記事を読んだ人は下記記事も読んでいます。

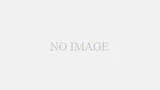
コメント