第1 本件請求は所有権に基づく返還請求(202条1項、200条1項)と構成できる。
第2 1 甲のAB間売買(555条)は税金の滞納による差押えを免れるためにAが「相手方」Bと「通じてした虚偽の意思表示」で無効である(94条1項)。そうすると、21年10月9日の甲のBD間売買によっても甲所有権が移転(176条)しないのが原則である。しかし、Dは「善意の第三者」として保護されないか(94条2項)。
2(1)同規定の趣旨は、虚偽の外観作出につき帰責性ある第三者よりも、外観を信頼した第三者を保護して取引安全を図る点にある。そこで、「第三者」とは、①虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者で、②虚偽表示を前提に新たに独立した法律上の利害関係を取得した者と解する。
(2)①Dは、虚偽表示たるAB間売買の当事者及びその包括承継人ではない。②Dは、AB間売買による甲所有権あるBを前提にBと売買をしたから、新たに独立した法律上の利害関係を取得した者と言える。
(3)よって、Dは「第三者」に当たる。
(4)また、Dは甲のAB間売買が仮装によるものであることを知らず、それを知らないことについて過失がなかったから「善意」と言える。
3 よって、Dは「善意の第三者」として保護され、同日甲のD名義の所有権移転登記も得たDは、確定的に甲所有権が認められる(177条)。
第3 Cは甲土地上の乙所有権を所有者Bとの売買により取得し、甲を占有している。
1 CはBとの間で、同年5月23日、乙所有目的で甲の賃貸借契約を締結した(601条、借地借家法2条1号)。Cは同売買に基づく所有権移転登記を得たから第三者に対抗できるとも思える(借地借家法10条1項、民法605条)。しかし、同賃貸借は他人物賃貸借(561条、559条本文)に過ぎないため、債権的に有効であるものの、甲所有者に対抗できないのが原則である。甲所有権がないBはCに甲を「使用、収益」(206条)させる権限がないためである。
もっとも、例外が認められないか。
2 Cは甲のAB間売買が仮装によるものであることを知っていたから「善意の第三者」として保護されない(94条2項)。
3 Aが同年12月16日に急死し(882条)、その息子で唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続した(887条1項、896条本文)。
(1) しかし、この時点で既にDが甲所有権を確定的に取得しているため、自己賃貸借にはならない。
(2)ア 他人物賃貸人は包括承継した他人の地位を併有するとして、具体的状況に応じて信義則(1条2項)で妥当な結論を導くべきである。
イ 他人物賃貸借をしたBが、「他人」Aの地位に基づいて追認(113条・116条類推)拒絶するのは信義則に反する。よって、同契約時の同年5月23日にさかのぼって自己賃貸借の効力が生じ、先に対抗要件を備えたCがDに優先するとも考えられる。しかし、そうすると「第三者」Dの所有権を害することになる(116条但書類推)から、そのようなことは認められない。
4 よって、例外が認められない。
第4 以上から、本件請求は認められる。
以上
【感想等】
所有権と占有それ自体まではオーソドックスですが、占有権原の話から複雑になっていきますね。
初学者の方は、まずはオーソドックスなところをきちんと書けるようにしていきましょう。
※この記事を読んだ人は下記記事も読んでいます。

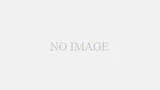
コメント